Ⅱ 最近の合唱について思うこと
<2003.2.1>
|
|
|
|
私の考える合唱とは、ベートーベンの第九の
「合唱」のような大合唱 |
|
ではない。せめて20人前後の訓練された歌い
手が、すべての |
|
ジャンルの曲を歌い分けるという、小回りのき
く合唱である。合唱と |
|
いうと大人数ではないと満足しない人が多い
が、合唱は人数さえ集まれば、 |
|
お金もかからず手軽にできる音楽である。しか
しその反面、これ程 |
|
難しくて、奥の深い音楽はないと思っている。
音楽大学の声楽家では、 |
|
昔から合唱を軽視する傾向がある。大変残念な
ことだ。一般的にも |
|
合唱音楽はマイナーなイメージがある。それは
なぜだろう。 |
|
|
|
よく「合唱臭い」という言葉を聞くことがあ
る。それはいくつかの |
|
要素がある。それはまず発声の面である。日本
人特有の響きの低く |
|
重い暗い声が、ソロの要素の強い、のどを鳴ら
す声作りをしてしまい、 |
|
ある作品(ジャンル)は対応できても、ほかの
ジャンルに適応できず、 |
|
歌い方が同じになってしまう。つまり、ルネサ
ンス期の宗教などの |
|
ハーモニーはすぐれているが、邦人作品の表現
(言葉)やポピュラー作品 |
|
なども「合唱」という一種独特な色に染まって
しまうことが多い。 |
|
また、技巧的な難曲でこれが合唱だと言わんば
かりに、独断的に迫って |
|
くるように思えるものもある。言葉(内容)は
ほとんど理解できない。 |
|
歌というより、音響デザイン的要素が強く、聴
く側は「これが現代音楽 |
|
なのか、難曲を見事に歌ってすごい!」とは思
うが、心の底からの |
|
感動が薄い。最近の中学・高校のコンクールで
も、このような選曲が多く、 |
|
残念に思う。皆同じように聴こえてしまうの
だ。技術的難曲の訓練も |
|
よいが、この時期は、詩、歌の中から心を学ん
でほしい。(続く)
|
|
|

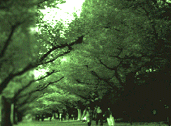
 このサイトは平松混声合唱団プロデュースによる、「心を豊かにする合唱鑑賞」を提案する情報サイトです。
このサイトは平松混声合唱団プロデュースによる、「心を豊かにする合唱鑑賞」を提案する情報サイトです。